はじめに
もし今、あなたが
- 誰かのためにと頑張っているけれど、なんだか報われないと感じている
- 人に頼られると、つい何でも「やってあげる」を選んでしまう
- 自分に自信が持てず、小さなことで立ち止まってしまいがち
そんな風に感じているとしたら、この記事があなたの心にそっと寄り添い、
明日からの日常に小さなヒントを届けることができるかもしれません。
私自身も、日々の生活や仕事の中で
「これで本当に相手のためになっているのかな?」
と立ち止まることがよくあります。

その「解決」、本当に相手のためになっていますか?
友人や知人が困っている時、あるいは仕事で同僚や部下が壁にぶつかっている時、私たちはつい「自分が何とかしてあげたい」という気持ちになりますよね。
例えば、資料作成で手こずっている同僚がいたら、
「ああ、私が作った方が早いから、代わりにやってあげようか?」
と声をかけたり、
複雑なタスクで悩んでいる部下がいれば
「ここは僕がやっておくから大丈夫」
と引き受けてしまったり。
もちろん、それは優しさであり、目の前の問題を速やかに解決し、物事をスムーズに進める上で有効な手段です。特に時間がない時や緊急を要する場面では、そうすることが最善の選択となることもあります。
しかし、ふと立ち止まって考えてみた時に、
「この問題は解決したけれど、次も同じことが起きたら、またこの人は同じところでつまずいてしまうのではないか?」
という疑問が頭をよぎったんです。
私たちの仕事は、ある程度ルーティンが決まっていて、「この時間にはこれをやる」といった流れがあります。そんな中で、「あ、またここでこの人はつまずくんだろうな」と予測できる場面があったりします。そんな時、私がその都度「やってあげる」ことで、確かにその場は滞りなく進みます。
でも、もしがその場にいなかったら?
もし私が手を差し伸べられなかったら?
その時、その人はどうするんだろう、と考えてしまったんです。
目の前の問題は解決できたとしても、それは一時的なものに過ぎません。相手が自分で解決する力を身につけない限り、同じ状況に直面するたびに、また誰かの助けを必要としてしまう。それは、本当にその人のためになっているとは言えないのではないか、と。
これは仕事に限ったことではありません。
例えば、人間関係でも同じようなことが言えます。
「この人とはどうも合わないから、距離を取ろう」という選択ももちろんありです。
無理に付き合う必要はありませんし、それが自分にとっての心の平穏を守るために大切なことである場合もあります。
しかし、仕事上など、どうしても避けられない接点がある場合、常に距離を取り続けることだけが解決策ではありません。もし、そんな相手との向き合い方、自分にとってストレスなく、かつ相手にとっても悪い方向に行かないような「手段」を知っていたとしたら、どうでしょう?
それは、また一つ新たな選択肢となり、あなたの心を少し楽にしてくれるかもしれません。

「自己解決能力」を育むためのヒントを渡す優しさ
何か問題が起きた時、それを代わりに解決してあげる、あるいは先回りしてスムーズに進むように準備してあげる――。
一見、親切な行動のように思えますが、場合によっては
「私がやってあげたんだから、あなたもこれくらいできるでしょ?」と、
無意識のうちに「貸し」を作ってしまうような関係になってしまうことがあります。
特に忙しい時ほど、「これだけやってあげたのに」という気持ちが芽生えてしまいがちです。
それが、かえって人間関係にぎくしゃくした空気をもたらしてしまうこともありますよね。
では、どうすれば本当に相手のためになるサポートができるのでしょうか。
私の気づきは、**「答えではなく、解決のヒントを渡す」**ということです。
「もし、ここでつまずいているなら、こういう考え方もあるよ」とか、
「この問題は、こういう方法で解決できるかもしれないから、ちょっと試してみて」
といったように、具体的な解決策を直接与えるのではなく、
相手が自力で答えにたどり着くための「手段」や「選択肢」を提示してあげるのです。
これは、相手の自己解決能力を育むことにつながります。
もちろん、最初からすべてを任せるのは難しいかもしれません。
時間的な余裕がある時や、少し落ち着いた状況の時に、「これはあなたに任せるけれど、もし困ったらこういうやり方も試してみてね」と、具体的なヒントを添えてみることが大切です。
例えば、
- 情報源を教えてあげる: 「この資料を探しているなら、あのデータベースに似た情報があるかもしれないよ」
- 思考プロセスを一緒に辿る: 「この問題のポイントは〇〇だと思うんだけど、あなたはどう思う?」と問いかけ、一緒に考える。
- 小さな成功体験を積ませる: 難しいタスク全体を渡すのではなく、まずは一部分だけを任せ、「ここまでできたら教えてね」と声をかける。
このように、相手が自分の力で乗り越えるための「道具」を与え、その使い方を教えてあげるイメージです。
そして、相手が自分の力で問題を解決できた時、そこには感謝以上のものが生まれます。
それは、相手自身の成長であり、自信であり、そして私たち側も、何かを「やってあげた」という見返りを求める気持ちではなく、「この人が成長できて嬉しい」という純粋な喜びを感じられるはずです。
(ここに、手と手が重なり合って、何かを一緒に掴もうとしているようなイメージ写真)
子どもとの関わりから学ぶ「手段を渡す」ことの価値
この「解決よりも手段を渡す」という考え方は、子育てにも通じるものがあるなと、最近特に感じています。
我が家には3歳になる子どもがいます。おもちゃのネジが固くて取れない時、すぐに「取って」とせがんできます。私にとってみれば、ドライバーを使えば簡単に取れることです。でも、そこで私がすぐに取ってあげるのではなく、「どうすれば取れるかな?」と一緒に考える時間を持つようにしています。
例えば、
- 「この道具(ドライバー)を使ったらどうかな?」と道具を指差して教えてあげる。
- 「こうやって回してみたら、ネジが緩むかもしれないよ」と、手の動きを一緒に真似してみる。
- 最初は少しだけ私が回してあげて、「あとは自分でできるかな?」と声をかけて見守る。
そうすると、子どもは「自分でできた!」という達成感を感じ、次からは自分でドライバーを持ってきて、ネジを回そうと試みるようになります。
最初はうまくできなくても、試行錯誤する中で「こうすればいいんだ!」という発見が生まれます。そして、その成功体験が、さらに「じゃあ今度はこれを組み立ててみよう!」「別のものも直してみよう!」という意欲につながっていくのです。
もし私が毎回すぐにネジを取ってあげていたら、子どもは「困ったらママがやってくれる」と考えるだけで、自分で解決する力や、新たなことに挑戦する意欲は育まれなかったでしょう。

これは、大人同士の関係でも同じです。
誰かの困り事を解決してあげることは、一見すると相手を助けているように見えますが、実はその人の成長の機会を奪ってしまっている可能性もゼロではありません。
もし今、あなたが
「せっかく手伝ってあげたのに、なんだかギクシャクしてしまったな」
「いつも私が解決してあげているのに、感謝されないな」
と感じているとしたら、それはもしかしたら、
「解決」する代わりに「解決の手段」を渡す、
という視点を取り入れてみる良い機会かもしれません。
おわりに
今日の話は、決して大きなことではありません。
日々のささやかな出来事の中で、私自身が気づいた小さな視点の転換です。
この小さな視点の変化が、あなたの周りの人間関係や、あなた自身の心のあり方に、
ちょっとした変化や、穏やかな良い影響があればと思います。
目の前の問題を一刀両断に「解決」することだけが、優しさや助け合いの形ではありません。
相手が自力で乗り越えるための「ヒント」や「手段」をそっと差し出すこと。
そして、その人の可能性を信じて見守ること。
それが、本当の意味で相手の未来を拓き、私たち自身の心にも温かい充実感をもたらしてくれるのではないでしょうか。
明日のあなたが、今日よりも少しだけ優しい気持ちで、そして、誰かの小さな成長にそっと寄り添えるような一日を過ごせますように。
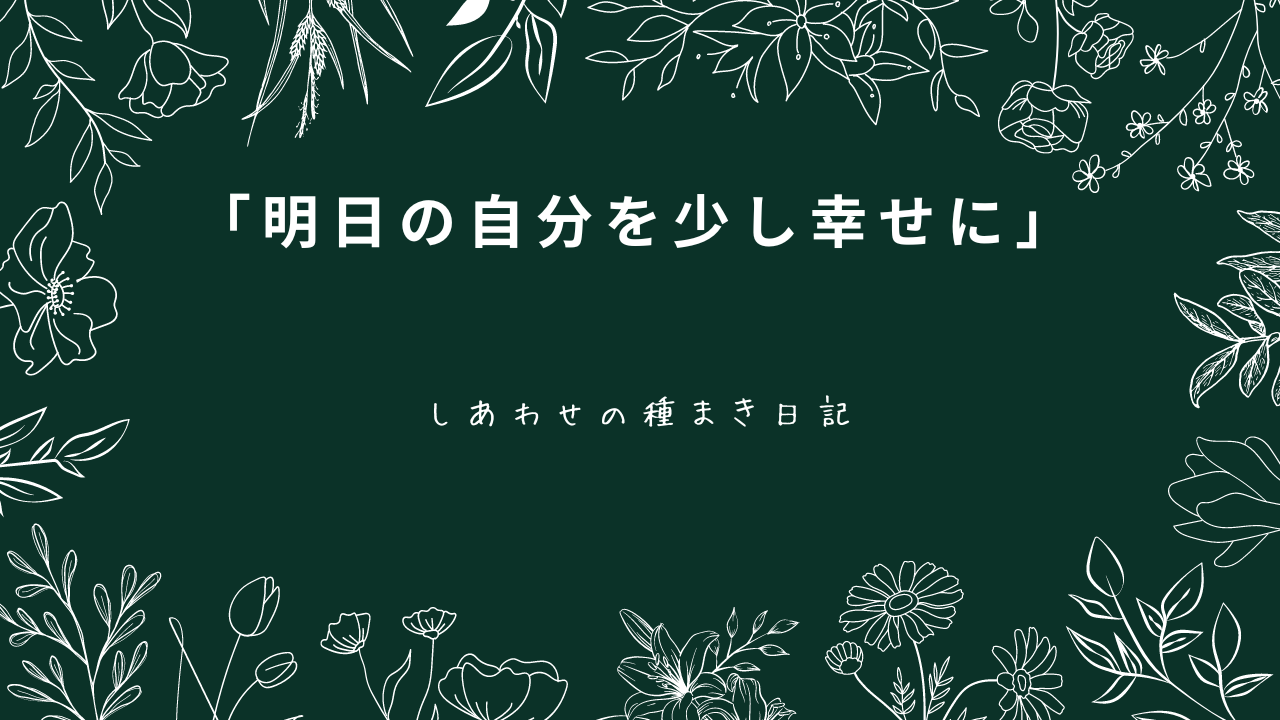







コメント